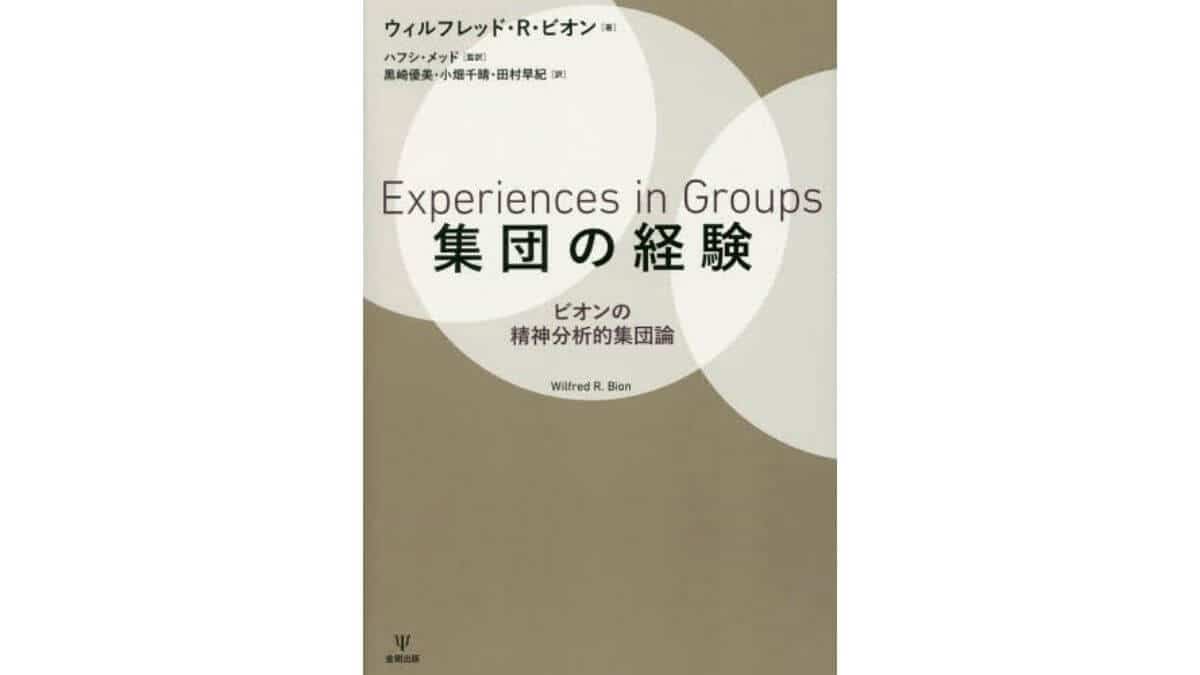集団心理学と自我の分析

「集団心理学と自我の分析」はフロイトの1921年の論文で、社会心理学的観点や集団心理学的観点から人間の心の成立や発達について包括的に論じている。対象関係論的な視点を盛り込み、今後の構造論への進化がうかがえる重要論文である。
集団心理学と自我分析(1921)の要約
(1)緒言
集団心理学とは、ここの人間をある部族、民族カースト、身分、期間の一員として、もしくは、ある時点で特定の目的のために集団へと組織化された人間の構成成分として取り扱う心理学。
集団心理学の現状は、ようやく端緒についたばかりであり、大量の個別問題を抱えている。
(2)ル・ボンによる集団の心の叙述
ル・ボン(フランスの社会心理学者)の著作「集団の心理学」からの抜粋を、精神分析の観点と比較しながら本章を進めている。
集団で、個々人に敷いてくる心の変化はどの点に存在するか・・・
各人が個人として獲得してきたものは集団の中ではその輪郭がぼやけ、それに伴い個人の独特さも消え失せる。
⇨精神分析的には…個人個人のもとで極めて多様に発達してきた心的上部構造は無力化し、誰にあっても同質の無意識の土台が露出させられると言うことであろう。
無意識の欲動への抑圧を払いのけることを許すような条件下におかれ、また伝染といつもに増して暗示されやすい状態ゆえに新たな性質をも示すようにもなる。
⇨伝染を個々のメンバーが相互に及ぼしあう影響に関係付けて説明することで精神分析的な最良の解釈を加えることになるであろう。
集団化した個人が集まると、個人としての抑制が全て消え去り、原始的な残虐では快適な本能が呼び覚まされる。
⇨精神分析が以前から証明している通り、子供や神経症患者の場合、真っ向から対立する観念が併存し両立しうるのであって、その際、論理的な矛盾から何らの葛藤も生じない。
集団は錯覚を求め、それを断念することができない・・・
集団は、非現実的なものと現実的なものの違いを認めない性向を顕著に示す。
⇨神経症患者には、客観的事実ではなく心的な現実の方が重みを持つことを見出している。
(3)ル・ボン以外の、集合的な心の生活の評価・検討
今までは大いに異なり合う形成体が「集団」として一括りにされてきたのであり、それらを区別して考える必要がある。
- 集団の形成持続時間(革命的な集団 ↔ 安定的な集団)
- 組織化という契機(組織性を持たない単純な群衆 ↔ 精神的同質性が高く組織化された集団)
集団形成にあって最も重要な現象は、各個人の中に引き起こされる情動性の昂揚という事態である。
情動性の昂揚…
- 集団の中では人間の情動が他の条件下ではないほどに大きく膨れ上がり個人として限界づけられている感情を失うほどだ。
- 集団が権威の担い手でありその制裁が恐れられることも、情動の昂揚を促進させているといえよう。
マクドゥーガル(イギリスの社会心理学者)によれば、集団の心の生活をより高い水準に引き上げるための主要条件とは、
- 一定の持続性
- 一定の表象があること
- 他の集団とライバル関係にあること
- 行事を持つこと
- 個々人に仕事が割り当てられていること
の5つを述べている。
(4)暗示とリビード
Q:何故我々は集団の中では判で押したように伝染なるものに従うのか。
A:集団が及ぼす暗示的影響こそが模倣の性向に従うよう我々に強要し、情動を誘発する。暗示こそ、人間の心の生活の、それ以上何ものにも還元不可能な根源現象、基本事実である。
・・・しかし、暗示の本質についてはすなわち十分な論理的根拠づけなしに影響の行使が起こる条件については結果として解明されるには至らなかった。
その代わりに、リビードの概念を用いてみよう。・・・
精神分析でいうリビードとは、愛としてまとめ上げることのできるものなら何であれ、そのすべてに関係する欲動のエネルギーの事である。愛は暗示の背後に隠されているもののようであり、下記着想から、集団の心についても愛の関係がその本質をなしているという前提が成り立つのではないか。
- 集団をまとめ上げる力はリビードであると考えられる
- 個人が独自性を放棄し、他者による暗示にかかるにまかせるのは、「彼らへの愛から」と考えられる
(5)二つの人為的な集団 教会と軍隊
指導者を欠いた集団と、指導者を伴う集団との区別を議論したく、その中でも高度に組織化され持続的で人為的な集団(例:教会と軍隊)に注目していく。
・教会と軍隊では、同じようなまやかし(錯覚)がまかり通っている。
まやかし:首長(キリスト、隊長)が集団のすべての個人を等しい愛情を持って愛している。
・軍隊のリビード的構造
大尉の一人一人が、いわば隊長にして父親であるという集団の階級構造から成り立つ。
→戦争神経症とは、軍隊の中で自分に割り当てられた役割に対して個々人が示した反発である。
・集団の本質は、集団の中にあるリビード的拘束のうちに存する
パニック現象:その集団が壊れて行く時に、集団の個々が自分しか気にかけなくなり、互いの拘束が働かなくなり、不安が解き放たれ、その結果生じる。
→Q:不安がなぜそれ程にも巨大になるのか?
A:パニック的不安は、集団のリビード的構造が緩んでしまったことを前提とし、その弛緩へのもっともなやり方での反応
(6)これに続く課題と仕事の方向性
集団を特徴づけるのがリビード的拘束である。二人の間の親密な感情的関係のうち比較的長続きするのは、ほとんどすべて拒否的で敵対的な感情の澱を含んでいるのであって、それがなんとか知覚されずに済んでいるのは、抑圧のおかげであるに過ぎない。
→こういう敵対心が、普段自分が愛している人に向けられる場合に、感情のアンビバレンツと呼び、他ならぬ親密な関係故に利害葛藤のきっかけもまた幾重にも重なっている。
・・・ところが、こういった非寛容のすべてが、集団形成によって、そして集団の中では一時的あるいは、持続的に消失する・・・
つまり、他人に対するリビードの拘束を通じて、ナルシシズムが制限される。しかし、所詮、他者との協力から引き出される直接的利益以上にナルシシズムの持続的な制限は成立しえない。
↓
言い換えると、集団の中ではナルシス的自己愛の制限が現れ、集団形成の本質が集団のメンバー相互間における新しいタイプのリビード的拘束の内に存在することを示唆している。
そのリビード的拘束とは?
集団にあって性的目標が問題になっているわけではないのは明らかである。感情の拘束という点で他の規制がさらに存在することを経験しており、それはいわゆる同一化である。
(7)同一化
同一化は・・・
精神分析において他の人格への感情的拘束の最も初期の発現として知れている。エディプスコンプレックスの前史の中で一つの役割を演じ、その下準備をする。男の子の場合…父親に対して:模範への同一化 母親に対して:性的な対象備給
↓
要するに同一化は始めからアンビバレントなのである。そして、父親との同一化が辿る運命は、後にはともすれば視界から見失われる。その場合には起こりうるのは、エディプスコンプレックスが逆転を経験し、女性的な姿勢の中で直接的な性欲動が充足を期待する対象として父親が選ばれるという事態である。
つまり・・・
○父親とそのように同一化すること
=そうありたい存在であること
=拘束が自我の主体において着手される
⇩
○父親を対象として選択すること
=それを持ちたい存在
=自我の客体において着手される
神経症の症状形成における同一化
症状形成がなされる状況(抑圧が起こり無意識の規制が支配しているところ)では、対象選択が再び同一化となる。
例)母親と同じように咳き込む少女
母親を敵視し、それに取って代わりたいという願望
今までの考察を要約すると…
- 同一化こそは対象への感情拘束の最も根源的な形態である
- 同一化は退行的な経過をたどり、いうなれば、対象を自我の中に取り込むことを通して、対象へのリビード的拘束に対する代替物になる
- 同一化は、性欲動の対象ではない人物との間にであれ、共通点が新たに知覚される度ごとに成立しうる
※この共通点が重要であればあるほど、それだけ一層この部分的同一化は首尾よく行われ、新たな拘束の端緒になる
(8)恋着と催眠状態
恋着:対象が自分の自我のように処遇されている。つまり、対象に向かって、より大きな度合いのナルシス的リビードが溢れ出している。対象が、到達できない自分の自我理想の代わりをする役目を負っている。
・恋着と同一化の比較
恋着:自らの最も重要な部分に代えてその対象を据える → 対象は保持され続ける →自我の側からもしくは自我を犠牲にして過剰備給される
同一化:その対象を取り込む → 対象は自我の内に再び打ち立てられる → 自我は失われた対象を模範として部分的に変容する
*洞察:対象は自我の代わりに置かれるものなのか、それとも自我理想の代わりなのか
・恋着と催眠の共通点
催眠術師が自我理想に取って代わると考えられ、自らの主導権が吸い上げられてしまうという事態が起きる点が共通している。
・集団のリビード的構成のための定式
一次的集団(一人の指導者をもち、過度の「組織化」によって二次的に一個体の性質を獲得できるのに至ったのではない集団)は、同じ一つの対象を自我理想の代わりに置き、その結果、自我が互いに同一化してしまった相当数の個人からなる。
(9)群棲欲動
集団は、情動的拘束(集団化した個人への転落)以上の特徴がある。それは・・・
依存:個人の散発的な感情の蠢きや、人格的で知的な行為があまりにも弱すぎて、単独では効力を発揮することができず、他者の側から同種の反復によって強化されるものを当てにせねばならないような状態
→トロッターの群棲本能からの説明:あらゆる同質的な生物は、リビードに発する傾向としてより包括的な単位に結合しようとする。
しかし、トロッターは集団における指導者の役割に対しあまりに僅かしか配慮しておらず、また、群棲本能が一時的ではないつまり分解可能なものであることがありうるという点で異を唱える。
・小さな子供の不安が向けられるのは母親であり、群棲本能など何も認められない。
群棲本能や集団感情が最初に形成されるのは、両親に対する子供たちの関係の中からである。つまり、兄弟児も自分と同様に両親に愛されているという事実に直面し、兄弟児と同一化するよう強制され、そのようにして集団感情が形成される。
そして、それは学校の中でさらなる展開を示す。
自分はどうせ贔屓されない→全員が公正に取り扱って欲しいという欲求→互いに同一化する。
・・・すると、後になって社会の中で共同精神、団体精神として働いているのが見出されるものも元来は妬みに由来するという素性が否認できない。
集団の平等への欲求が、その集団の個々のメンバーにしか当てはまらず、指導者には当てはまらない。
→結論:すべての個人は互いに対等であるべきだ、しかし、彼らは誰もが一人一人の人に支配されることを望む。人間とは、群棲をなす動物というより群族をなす動物(一人の首領によって先導される群族に属する個体的存在)なのだ。
(10)集団と原始群族
集団形成が習慣として人間を支配している限り、その中には原子群族が存続しているのを、我々は認める。
→集団の心理とは最古の人間心理である。
集団の原父—原父に代替する息子との関係:原父は集団理想であり自我理想に取って代わって自我を支配しており、原父は息子を言うなれば集団心理へと強要する。
↓
催眠(暗示)においても、催眠術師と催眠を体験する者との間で生じる集団形成の不気味で強制的な性格はそれに由来するという事実に帰されるだろう。
(11)自我の一つの段階
集団のリビード的構造を解明する上で我々がなしえた貢献:自我と自我理想の区別、そして、この区別によって可能となる二重の拘束(同一化・自我理想に変わる対象の投入)に帰着する。
→自我の中にそのような段階を想定することは自我分析の第一歩をなす。
- 躁病:自我と自我理想とが交流しており、その結果、人格はいかなる自己批判によっても妨害されることなく勝利と自己喜悦の気分に浸流。
- 自然発生的なメランコリー:自我理想には特別の厳格さを発揮しようとする傾向があり、そのせいで自動的に自我理想の一時的たな上げという結果に至る。
- 心因性のメランコリー:自我は非難されている対象と同一化しているせいで理想の側から虐待され、その虐待経験によって反抗へと刺激されるのだろう。
(12)補遺
今まで述べてきた中で、よけておかれた洞察を複数補足している。
(13)感想
- 初めてフロイトの論文をじっくり読む機会となりました。まだまだ理解が及んでないのですが、フロイトの思考能力の凄まじさが伝わってきて、ここまで高い思考能力を持つと生きづらかっただろうなぁと思いました・・・。
- 集団の愚かさ(戦争や大量虐殺の大規模なもの〜会社での集団による判断ミスといった小さなもの)を想像しながら読み進めました。
(14)みんなで議論したい点
皆さまがされている個人療法や集団療法の中で、本論文で得た知見が役立ちそうな観点はありましたでしょうか?
集団心理学と自我の分析(1921)の解説
(1)成り立ち
本論文は、1919年春にアイデアが浮かび、1920年2月に研究を始め、8月には草稿が完成した。そして、1921年3月に完成し、その3~4ヶ月後に出版された(ストレイチー)。フロイトはロマン=ロランに向けて「この著作がとくによく書けているとは思いませんが、個人の精神分析から社会の理解への道を示していると思います」と手紙を送っている。
「トーテムとタブー(1913)」において、社会や集団の影響の元で生成される個人心理について論じたが、それに対象関係論的な視点や新たな防衛機制から再度論じなおしていると言える。
「トーテムとタブー(1913)」の内容については以下に詳しく掲載しています。
(2)フロイトの集団についての認識
フロイトは集団について、散々に酷評している。人々は集団になると興奮し、分別がつかなくなり、非論理的になり、感情的になり、短絡的になるとしている。確かにそういう面はあるかもしれない。これは100年前にフロイトが書いたものだが、現代でもそう変わらないところはあるかもしれない。
民主的なことを求めている集団が非民主的な振る舞いをしたり、平和を訴えているのに暴力的なことをしたり、人権を大事にすることを目的にしている集団であるにも関わらず人権侵害を平気でしたり、対話を重視するといいながら脅迫的に支配しようとしたり、個人を尊重するとしながら弾圧したり、など例をあげればきりがないくらいである。
こうしたことは、現代風にいうと集団になることにより、妄想分裂ポジションの側面が刺激され、活性化されるとでも理解できるかもしれない。こうしたことを見るとフロイトの観察眼は鋭いと言わざるをえないかもしれない。
(3)フロイトの集団の中での振る舞い
一方で、フロイトが自身の精神分析サークル内での言動や振る舞いを見ると、どうなるだろうか。フロイトは精神分析の創始者であるという立場であるがゆえに、好むと好まざるとに関わらず、集団の頂点に位置付けられていた。フロイトは権威であった。フロイトの弟子たちが論考を発表する際にはほとんどの場合フロイトに伺いを立てていたようである。
フロイトの愛を享受しようという弟子たちの間の兄弟葛藤は非常に強かったことが容易に想像できる。また、フロイトもそうした中で、弟子の扱いに差をつけ、ある弟子には手厚く、ある弟子は冷遇した。フロイトと弟子と女性を絡めた三角関係も多々あった。フロイトは厳父であり、モーゼであったと言えるだろう。
フロイト精神分析サークルから離反をした弟子たちは、その多くが不幸な末路をたどっている。発病したもの、自殺したもの、破滅的な行動にはしったもの。ユングなどは一時的に急性精神病状態であったようだが、もちなおし、それを創造的に理論と臨床につなげた稀有な存在であろう。
フロイトの死後はフロイトの後継者争いは相当な激しさであった。アンナ・フロイトとメラニー・クラインの間の大論争である。大論争では彼女ら二人の弟子をも巻き込み、紳士淑女協定ができるまで苛烈に続いた。そこには科学的な論争ではなく、感情的反発や情緒的攻撃が相当あったようである。
こうした状況を鑑みると、フロイトのパーソナリティの影響はあったろうが、フロイトそのものが集団の中で非理性的、非論理的、感情的、権威的に振る舞っていたようである。集団の中で思考することがどれほど難しいのかを我々に教えてくれる事例とも言える。
(4)中期理論と後期理論の橋渡し
本論文はフロイト精神分析理論の中期と後期の橋渡し的な位置づけにあると考えられる。
a.同一化という観点から
まず集団、他者からの取り入れや同一化により、自我理想や審級を獲得するというアイデアは、「喪とメランコリー(1917)」の延長にあたるだろう。フロイトによるとメランコリーの自責感は自分に取り入れられた他者に対する怒りや攻撃性であるとしている。
これらは「対象の影が自我に落ちる」という詩的で美しい表現に端的に示されている。こうしたアイデアが本論文でも取り入れられており、集団の規範を取り入れ、それを自身の良心、自我理想、審級とする観点はまさに対象関係論的であると言える。
フロイトの重要論文「喪とメランコリー(1917)」については以下をご参照ください。
b.超自我という観点から
また、本論文に登場する自我理想や審級は、2年後の論文「自我とエス(1923)」で詳しく論じられている超自我に連なる概念である。本論文ではまだ超自我と死の欲動の密接な結びつきが不十分であるが、それでもその萌芽を見て取れる。こうした概念はもちろん構造論として確立されていくこととなる。意識、前意識、無意識という局所論から構造論への進化、もしくは拡充は今後の精神分析的自我心理学へと発展していく。
「自我とエス(1923)」の要約と解説は以下をご覧ください。
一方で、超自我、死の欲動(羨望)、ナルシシズムの三者が結びつき、クライン派精神分析における病理構造体、パーソナリティの病理として結実していくこととなる。
c.分裂という観点から
心の中に様々な自分がいるという観点は「分裂」という現代精神分析では欠くことのできない論点であり、精神分析臨床的にも有用な概念である。つまり、自分には理解できず、思うように統制できない自分がおり、その影響が意識以上に強いということである。そして、それらの間の乖離が強いと病的な状態となってしまう。フロイトの有名な「エスあるところに自我あらしめよ(自我とエス 1923)」という格言の端緒になっている。こうした治療戦略がフロイトの基本的なスタンスであった。
ただ、これらはその後のラカン心理学からの批判もある。つまり、主体の問題なのである。自我は自分の機能1つであり、主体ではないというのが主な批判である。確かにそれはそのとおりであり、自我はさまざまな機能と役割をもつ自分の中の単に一つであり、それはその個人の全てであるとは到底いえない。
では、主体とは何か、主体とはどこにあるのか、は現代にまで続く論点である。この点に関してはウィニコットはニードの問題として理解し、ビオンはO(オー)の問題として吟味していったようにも考えられる。
d.不安理論の観点から
最後に、本論文には不安理論の今後の改訂に先立つ点も垣間見れることができる。これまで欲動の抑圧の結果、不安が現れるとフロイトは考えていた。しかし、5年後の論文「制止、症状、不安(1926)」では、不安信号説に取ってかわることとなる。
その不安信号説になくてはならないのが、ここで取り上げられている超自我や自我の防衛機制の観点である。超自我(審級、自我理想)とエスと外界から脅かされる事態に対して生じるのが不安であり、そうした不安の対処として自我が防衛機制を発動するのである。その不安理論の改訂のための準備は本論文で既に出来つつあるといえるだろう。
このように本論文は精神分析における、取り入れ同一化の発展、超自我への発展、不安理論の改訂の前駆期、自我機能と分裂と主体の問題、といった論点が交差するところにあると言える。そうした意味でのフロイト精神分析理論の中期と後期を繋ぐ論文と言えるだろう。
「制止、症状、不安(1926)」を知りたい方は以下のページをご覧ください。
(5)自我分裂
本論文でもフロイトは様々な役割をもつ自我について述べている。それぞれの自我は互いに相容れず、そのパワーバランスの中で思考や行動が決定されるのである。つまり、人間は統合された一つの意思に基づくのではなく、そもそもがバラバラになっているものである。超自我・自我・エスという構造論にしても、それぞれが別の機能を担っているのである。
「フェティシズム(1927)」や、「防衛過程における自我の分裂(1940)」という未完のたった数ページしかない論文でフロイトは否認の機制とその帰結としての分裂について触れている。さらに「神経症と精神病(1924)」において、精神病の特徴の一つとしても挙げている。
メルツァーは「クライン派の発展(1978)」において、フロイトの理論変遷を分裂という概念を含めるか含めないかの揺れ動きという観点を軸にして講義している。
分裂という概念は知っての通り、フェアバーンに始まり、クラインがポジション論に組み入れ、人間のプライマリーな防衛機制として重要な位置づけを与えた。分裂は病理であると同時に、精神病的な不安に対する防衛でもあり、それはひいては神経症的な健康な防衛に引き渡す前の過渡的なものである。もちろん健康な成人でも分裂は使用するが、部分的であり、一部である。
退行し、分裂が全面的に展開すると多大な障害を引き起こしてしまう。そして、パーソナリティ障害などではそうした防衛が恒常的に作動しているともいえる。
(以下の「喪とメランコリー(1917)」を再掲)
(6)集団精神療法の発展
本論文では、主にフロイトは集団と言いつつ、社会という大きな視点で集団を捉えていた。その集団から個人に対して与えられる影響が本論文のテーマである。と同時に、集団からの影響を個人内における内的プロセスとしてどのように受け取り、どう生成し、人格の発達に組み込んでいくのか、という個人内心理学の観点も含められている。
こうした点は、人間の成り立ちに関する理論といえる。
しかし、小集団と個人との関連性はほとんど扱われていない。特に集団精神療法という視点はフロイトにはなかったようである。以下に現代までにつながる集団精神療法について概観する。
a.フークスの集団精神療法
ドイツ出身の精神分析家であり、のちにアメリカに移民した。彼は自身のアプローチを「集団による精神分析」と呼称した。メンバーが他メンバーに対する共同治療者になるために、集団メンバーの治療能力が発達することが重要であるとした。精神分析家の役割はその発達を促進させ、コミュニケーションを活用することにある。
転移の扱いについては、集団からの精神分析家への転移は考慮に入れられるが、メンバー間の転移は除外されている。
b.ビオンの集団精神療法
図1 ウィルフレッド・ビオンの写真
厳密にはビオンは精神分析家になる前に実施していたものなので、精神分析の範疇に入るかどうかの問題がある。
ビオンは陸軍病院で集団精神療法を実施していた。数名のメンバーとセラピストからなる治療を目的とした集団によって定期的な会合がもたれる。そのグループの在り方をビオンは作業集団と基底的想定集団との分類できる。それら二つは固定したものではなく、プロセスによって変転していくものである。
前者は治療という本来の目的に沿ってグループが動いている時であり、抑うつポジションに相当する状態である。後者は本来の目的から逸れ、病理的なあらわれが前面に出てくる状態である。基底的想定には3つの下位状態があり、「依存」「闘争-逃走」「つがい」である。
依存では、メンバーのそれぞれが主体的に何かをしようとすることはなく、セラピストや他メンバーが何かをしてくれるだろうと期待し、それをいつまでも待っており、グループの進展は自分以外の誰かに依存しているというものである。このような依存の背景には、自分自身は頼りにならないが、セラピストは頼りになるという無意識の想定があると思われる。
闘争-逃走では、グループ内で対立や言い争い、諍いが発生している状態である。ここでは敵か味方かという二極化した思考となり、迫害的な心性が顕著となっている。
つがいでは、グループ内にペア・カップルが生まれ、その二者の間で延々と対話が続き、グループ全体がそこに何らかの変化が起きるのではないかという期待を通してみてしまうことを指す。そこには魔術的に救われるだろうという幼児的な願望が潜んでいると考えられる。
また、3つの基本的想定に加えて、4つ目の状態を付け加えたのがTurquet,Pである。それは「一体想定」と呼ばれるもので、メンバーはそれぞれの個性を捨て、全能と想定されるグループの力に受身的、受動的に一体化し、空虚な幸福感に飲み込まれる状態のことである。
いずれの基底的想定においても、不安に対する原始的な防衛の形態であり、妄想分裂ポジションに相当するあり方と理解できる。
c.現代の集団精神療法
ここでは鈴木の方法を紹介する。
集団精神療法とは多くの患者を一時に治療することが目的ではない。患者間の相互コミュニケーションを通して、自身の病気、性格、考え方、生き方などを理解していくための装置である。また、デイケアやレクリエーション、スポーツ、工作、料理、グループワークなどの課題が明確で、みんなで一緒に取り組むようなものから、1時間などで時間を区切り、主に対話を通して行っていくものまで様々ある。が、より後者にちかいものを集団精神療法としている。
集団精神療法の方法として、話題や議題は設定せず、思いつくままで自由連想的に話し合うことから始まる。話し合いの前提条件としてグループ内では治療者を含めてメンバーは全て平等であり、どんなことを話しても良いし、話したことによる不利益はないということが保証される。人数は、7~8人の小グループ、15~20人の大グループ、数十人のコミュニティグループなどがあり、メンバーの数によってグループのあり方や治療目標も変わってくる。
治療者は外的構造(時間、場所など)を維持する役割があり、メンバーを選定する責務を担う。集団精神療法内では中立を保ち、相互コミュニケーションを促し、時には解釈を行う。治療者であると同時にメンバーの一人であるという二重の役割を背負っており、グループ内での経験を共有する一人でもある。
集団精神療法を実施する際、特異的に注意せねばならないことがある。日本では個より全を優先するメンタリティがあり、幼少期から周囲に合わせて、適応することが良いこととされてきた。このことは集団精神療法でもそれが働き、ことあるごとにグループ全体の意思や感情を確認し、それに適応しようとする動きが出てくる。これをグループとしての凝集性が高まっていると誤解してしまうことがある。また、治療者はグループを操作的に用いてしまうことがある。
治療者は治療場面に慣れており、メンバーを選定することをしているが故に主導者的な役割を取ってしまいがちである。同時に、メンバーにサービスをし、過度にフォローしてしまうこともよくある。こうしたことを乗り越えるために、治療者は自身が集団精神療法の経験をしたり、スーパービジョンを受けたりする必要がある。
d.ヤーロムの集団精神療法の治療機序
図2 ヤーロムの写真
ヤーロムは集団精神療法の治療機序として以下の11を挙げている。
- 希望をもたらす
- 普遍的体験
- 情報交換
- 愛他的体験
- 家族の中で体験したことの繰り返し
- 対人関係スキルの向上
- 模倣を通して自分の行動を考える
- 対人関係から学ぶ
- グループ凝集性
- 表現・カタルシス
- 究極的には一人で現実に対決し責任を取る
さいごに
フロイトの創始した精神分析について興味のある方は以下のページを参照してください。
参考文献
この記事は以下の文献を参考にして執筆いたしました。
- 小此木啓吾 監修(2002)精神分析事典 岩崎学術出版社
- J.M.キノドス(2004/2013)フロイトを読む. 岩崎学術出版社
- ストレイチー(2005)フロイト全著作解説 人文書院
- W.R.ビオン(1961)集団の経験. 金剛出版
- S.フロイト(1905)性欲論三篇
- S.フロイト(1913)トーテムとタブー
- S.フロイト(1917)喪とメランコリー
- S.フロイト(1920)快感原則の彼岸
- S.フロイト(1923)自我とエス
- S.フロイト(1924)神経症と精神病
- S.フロイト(1926)制止、症状、不安
- S.フロイト(1927)フェティシズム
- S.フロイト(1940)防衛過程における自我の分裂
- メルツァー(1978/2015)クライン派の発展 金剛出版
- I.ヤーロム(1970)グループサイコセラピー 理論と実践. 西村書店