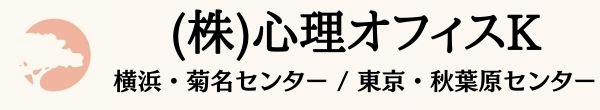優しいカウンセラーの功罪について

一般的なカウンセラーのイメージには優しいなどがあります。実際のカウンセリングではそうしたことが虚構である場合もあります。これらについて書いています。
カウンセラーのイメージ

カウンセラーの一般的なイメージにはどういうものが多いでしょうか。
- 優しい雰囲気
- 柔らかい表情
- にこやかな笑顔
- 受容的な話し口調
- 和んだ空気.etc
こういうところがよく言われるところだと思います。基本的にカウンセリングを仕事をするカウンセラーは人のために何かをしたいという思いが強いし、助けたい、癒したいという気持ちが強いと思います。そのため、上記のような印象を持つ人は多いかと思います。
「優しいカウンセラー」とは、クライエントに寄り添い、安心感を与える存在として重要な役割を果たします。しかし、その優しさが過度になると、本来直面すべき課題や感情を避ける関係性を強めてしまうことがあります。クライエントは一時的に癒されても、問題の核心に触れられず、依存や停滞を招くことがあります。カウンセリングには慰めだけでなく、苦痛や葛藤を共に扱う中立性が不可欠であり、そのバランスが変化と成長を促す鍵となります。
よくある相談の例(モデルケース)
40歳代 女性
Aさんは40歳代の女性で、幼少期から家庭内で感情を自由に表すことが難しく、常に周囲に気を配りながら過ごしてきました。大人になってからも人間関係の疲れや孤独感を抱え、心療内科で軽い不安症と診断されましたが、薬物療法だけでは根本的な苦しさが変わらず、紹介を受けてカウンセリングを開始しました。
初期の面接でカウンセラーはAさんの不安や葛藤に強く共感し、「無理をしなくてもいい」「Aさんは十分に頑張っている」と優しい言葉を多用しました。当初、Aさんは安心感を得て涙を流し、受容された体験に癒されるように感じました。しかし、時間が経つにつれて、Aさんはセッションで自分の苦しみを繰り返し語るだけになり、根本的な問題には触れられないまま停滞していきました。カウンセラーも否定的な感情を抱かせまいと過剰に配慮し、葛藤や矛盾に切り込むことを避けたため、表面的なやり取りが続きました。
次第にAさんは「ここでは安心できるけれど、日常には戻りたくない」という感覚を強め、現実の人間関係の中で困難に直面するたびにカウンセリングに依存するようになりました。セッションを重ねるほど安心感は増したものの、自らの感情や他者との関係を変化させる力にはつながらず、閉じられた関係の中で膠着が進んでいきました。やがて、Aさん自身も「通っているのに変わらない」「ここだけが安心で外ではつらい」と不満を募らせ、カウンセラーへの依存と怒りが交錯するようになりました。
この状況を契機に、カウンセラーは自らの姿勢を振り返り、優しさによってAさんの回避や依存を強化してしまったことを認識しました。そこからは、あえてAさんの矛盾や逃避に触れ、苦痛を伴う場面を共に扱うことに方向転換しました。Aさんは当初強い抵抗を示し、セッション後に疲労感や怒りを抱くこともありましたが、徐々に「嫌な気持ちを表しても関係は壊れない」という新しい体験を積むようになりました。
数年にわたるプロセスの中で、Aさんは「優しさに守られるだけでは変われない」という気づきを得て、困難を引き受けながら自分の感情や欲求を言葉にできるようになりました。その結果、職場でも自分の意見を伝える勇気が生まれ、人間関係の中で以前よりも自由さを感じられるようになりました。
カウンセリングにおける否定的な感情の表出
しかし、実際のカウンセリングの場ではそれだけで充分ということはありません。クライエントさんから酷い言葉を投げかけられたときにもお釈迦様のように受容できる人は良いかも知れないですが、なかなかそういうことはできないものです。
きちんとそういう怒りや攻撃性を投げかけてくるクライエントさんに向き合っていかねばなりません。時には厳しくならなければいけないときもあるし、場面によっては怒ることもあります。ビシっと対応せねばならない局面も多いと思います。
カウンセリングにおいて優しい対応、受容的な雰囲気は大切ですが、それが過剰だと、クライエントさんが本来持っている怒りや攻撃性を出しづらくなります。それらを出すことに罪悪感を抱くのかもしれません。また、カウンセラーが過剰に謝ったり、へりくだったり、取り繕ったりすると、本当は出したかった怒りを出せなくさせてしまいます。この本来的な怒りと攻撃性をカウンセリングの場でワークスルーしていくことが大事です。
Aさんは、安心を与えられる言葉に守られるうちに、次第に不満や怒りといった否定的な感情を抱くようになりました。カウンセリングが進まないことへの苛立ちや、依存と反発が交錯する気持ちが生じ、セッションの中で戸惑いながらもそうした感情を少しずつ表現するようになりました。
カウンセラーの中立性
といっても、カウンセリングでカウンセラーがミスを全く謝らないとか、常にピリピリした雰囲気を出しておくというのもまた違います。つまり、あまり不自然に優しさも厳しさも出さずに、そのカウンセラーの本来の雰囲気のまま中立性を保つことが大事だと思います。カウンセラーは完璧なスクリーンになることはできませんが、それを目指すことは大事です。そのための訓練として教育分析や個人分析、スーパービジョンなどをカウンセラーは受けているのです。
上に書いたように過剰な優しさをだすカウンセラーはメシアコンプレックスや過剰な償い、罪悪感をクライエントさんに抱いているのかもしれないし、その背後にはカウンセラー自身の怒りや攻撃性を抑圧しているとも言えるかもしれません。
Aさんの場合、当初カウンセラーは優しさを重視しすぎたため、中立性を保つことが難しくなっていました。その結果、Aさんの依存を助長し、問題を回避する関係が強まっていました。しかし、カウンセラーが中立的な立場に立ち直ることで、Aさんは自分の否定的な感情を安全に表す場を持てるようになりました。
カウンセラーが提供できるもの
色々なクライエントさんがいますが、クライエントさんによってはカウンセリングでカウンセラーに優しさや共感や受容を求めることはありますし、それは間違いではないと思います。それまでに辛く苦しい経験をしており、今にも折れそうな思いできているので、そこでサポートしてもらいたいという気持ちはよく分かります。また、できればそれに応えていきたいとも思います。しかし、そういう気持ちを理解することと、現実的にそれを提供することとはまた違います。
クライエントさんの希望に沿わないということではないですが、優しい態度とにこやかな笑顔には功罪があるということを理解していくことがまずは大切だと思います。
Aさんは、優しさだけでは変化につながらないことを経験しました。カウンセラーが提供できるのは、単なる慰めではなく、時に不快や葛藤を扱うための安全な枠組みです。その中でAさんは、困難に耐えながらも自分の感情を言葉にし、新しい関係の可能性を模索できるようになりました。
スーパービジョンを受けたい
カウンセリングの現場では、クライエントに安心を与えたいあまり、過度に「優しさ」に傾き、結果としてプロセスが停滞することがあります。表面的には穏やかに見えても、深い課題に踏み込めず、関係がこじれてしまうことも少なくありません。こうした局面では、カウンセラー自身が自らの姿勢を振り返り、専門的な視点で整理することが求められます。スーパービジョンでは、優しさと中立性のバランスを臨床的に検討し、より効果的な支援方法を見いだすことができます。経験豊富なスーパーバイザーとの対話を通じて実践を深めたい方は、ぜひお申し込みください。